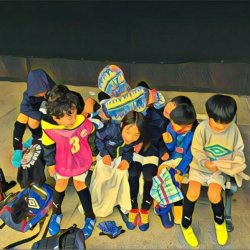(内藤です。
こちらの総括、岩崎コーチには随分前に頂いていたのに、内藤がうっかりしてアップするのを失念していました。保護者の方にご質問をいただきその事に気づいての対応です。掲載が遅くなってしまい誠に申し訳ありません。)
——
コーチの岩崎です。
5月5日に5年生Bチームの順位決定リーグ戦が開催されました。5年生は5名のみの参加ということで、4年生5名の力を借り、試合前に自己紹介も兼ねながらアップするという急造チームでの参戦です。
この日の目標は予選に引き続き「最後まで諦めないこと」にしました。ボールを最後まで諦めずに追いかけること、ドリブルで抜かれても諦めず食らいつくこと、得点をたくさん入れられても最後まで戦い抜くことを約束事にしました。
結果だけ見ればとても悔しいものになりますが、各選手が現時点の自分の課題を認識し、それを次に繋げるためにどのような行動に実践できるか、今後の成長に期待出来る試合になりましたので、以下総括します。
【1試合目】
vs猿楽 結果:0vs10(●)
予選リーグで富ヶ谷Aチームと引き分け、得失点差でリーグ3位になった猿楽が初戦の相手でした。強豪相手ということで、しっかりと今日の約束事を守りつつ、まずは守備をしっかりとしてチャンスを待つ戦術にしました。
が、やはり相手は強豪。パスをどんどん回してゴール前に近づいてきます。GKりくの堅実なセービングも多々ありましたが、ゴール前に転がったボールを相手FWがいち早くゴールに繋げられ得点を重ねられました。ただ、失点の多くが完全に守備を崩され止められなかったというものではなく、ゴール前に転がったボールにあと1歩2歩早くチェック出来れば防げたものでした。
なぜ大量得点になってしまったのか。それは試合後のミーティングでも選手達には伝えましたが、「消極的(他人任せ)な姿勢」が原因です。この初戦、積極的にボールに関与出来た選手はふうか・はるたの2名のみで、その他の選手はとても消極的(他人任せ)でした。もっと積極的な選手が多ければ、ゴール前に転がったボールを相手FWより早くクリア出来ていたものと考えます。
【2試合目】
vs美竹 結果:1vs4(●) 得点者:ふうか
初戦の反省も踏まえ、より一人一人が積極的にボールを追いかけることを約束事に追加しました。前半は選手一人一人が約束事を意識し、ひるむことなくボールを追いかけることが出来ました。その成果として予選・決勝を通じて唯一の得点を取ることが出来ました。初戦でも積極的なサッカーをしていたふうかがゴール前での混戦から見事にシュートを決め、リードしたまま前半を終了。後半も引き続き積極的にボールに関与して仲間を助けようと指示を出して送り出しました。
後半、美竹はより積極的にボールを追いかけてくるチームにレベルアップしてきました。
なかなかボールを支配出来ない展開の中、逆転されてしまうと、それまで積極的にボールを追いかけられていた選手の足が少しずつ止まってしまい残念な敗退になりました。
【3試合目】
vs渋谷東部B 結果:0vs5(●)
相手の渋谷東部Bチームは、予選リーグでも負けたチームということでリベンジマッチになります。選手達もリベンジを果たしてやるのだという意気込みと最後まで諦めないガッツを持って試合に臨みます。
ただ、この試合においては、富ヶ谷Bチームの選手の多くがエネルギー切れで動けなくなり、それを頑張って動ける選手がカバーしようとしてフォーメーションが崩壊するという悪循環により、相手に良いようにボールを支配されてしまいリベンジはまた次回に持ち越しになりました。
【課題・改善点】
まだまだ成長の伸びしろがたくさんあるメンバーの試合なので、課題を挙げてしまえばキリがないです。ただ、一番大事なことは、選手達が3試合を通じて「自分の課題が何かを認識しているかどうか」です。急造チームでしたので、フォーメーションやパスワーク等のチームとしての課題は棚に上げてしまって良いかと思います。一方で個人の課題を各選手が挙げられるか、そしてそれを改善するように行動に移せているかどうかが、今後の成長の伸びしろの幅を決めていくものと考えます。試合直後は負けて悔しいと思っていた選手が、試合後1週間以上が経過した今、大小問わず何らかの行動に移せた選手が何人いるでしょうか。
全体的に控えめな性格の選手が多いチームですが、もう1歩早く、大きく踏み出して行動する積極性を持つことが、今の課題を克服し、更なる成長に繋がっていくと信じ、引き続きサッカーに真摯に取り組んでもらいたいと思います。
【良かった点】
最後まで気持ちで諦めてしまった選手がいなかったことです。体力切れで体が動かなってしまっても、最後までなんとかしようともがけたことは、将来的な成長に繋げるための大切な要素なので、今後の成長に期待出来ると考えます。
スポーツにおいて一番成長出来るのは、自分の感覚に自分の身体/運動能力が合わせられるようになる時です。タイミングとしては基礎運動能力が発達する小学校低〜中学年と、肉体的に成長期を迎える中学〜高校の2回のタイミングがあります。
今は基礎運動能力に差があるにせよ、これから迎える成長期でそれをカバーして余りあるくらいに成長出来るタイミングが訪れます。その時に自分が好きなスポーツに一生懸命に取り組めていることが重要で、そのためには「諦めずに頑張れること」はとても大切です。バカにしてくる奴もいるかもしれません(富ヶ谷SCでそんな事をする選手は断じて許しませんが)。でも、今後迎える成長期に、そのような奴らを追い抜くタイミングが必ず来ますので、諦めずに頑張ることがとても大事な成長の鍵になります。
あえて上記では「自分が好きなスポーツ」と書きました。出来ればサッカーを続けていてほしいと思う一方で、人生にはたくさんの選択肢があり、それぞれに無限の可能性がありますので、積極的に自分のやりたいことを見つけ、どんどん一歩を踏み出せる選手・人に成長してもらいたいと願っています。
こちらの総括、岩崎コーチには随分前に頂いていたのに、内藤がうっかりしてアップするのを失念していました。保護者の方にご質問をいただきその事に気づいての対応です。掲載が遅くなってしまい誠に申し訳ありません。)
——
コーチの岩崎です。
5月5日に5年生Bチームの順位決定リーグ戦が開催されました。5年生は5名のみの参加ということで、4年生5名の力を借り、試合前に自己紹介も兼ねながらアップするという急造チームでの参戦です。
この日の目標は予選に引き続き「最後まで諦めないこと」にしました。ボールを最後まで諦めずに追いかけること、ドリブルで抜かれても諦めず食らいつくこと、得点をたくさん入れられても最後まで戦い抜くことを約束事にしました。
結果だけ見ればとても悔しいものになりますが、各選手が現時点の自分の課題を認識し、それを次に繋げるためにどのような行動に実践できるか、今後の成長に期待出来る試合になりましたので、以下総括します。
【1試合目】
vs猿楽 結果:0vs10(●)
予選リーグで富ヶ谷Aチームと引き分け、得失点差でリーグ3位になった猿楽が初戦の相手でした。強豪相手ということで、しっかりと今日の約束事を守りつつ、まずは守備をしっかりとしてチャンスを待つ戦術にしました。
が、やはり相手は強豪。パスをどんどん回してゴール前に近づいてきます。GKりくの堅実なセービングも多々ありましたが、ゴール前に転がったボールを相手FWがいち早くゴールに繋げられ得点を重ねられました。ただ、失点の多くが完全に守備を崩され止められなかったというものではなく、ゴール前に転がったボールにあと1歩2歩早くチェック出来れば防げたものでした。
なぜ大量得点になってしまったのか。それは試合後のミーティングでも選手達には伝えましたが、「消極的(他人任せ)な姿勢」が原因です。この初戦、積極的にボールに関与出来た選手はふうか・はるたの2名のみで、その他の選手はとても消極的(他人任せ)でした。もっと積極的な選手が多ければ、ゴール前に転がったボールを相手FWより早くクリア出来ていたものと考えます。
【2試合目】
vs美竹 結果:1vs4(●) 得点者:ふうか
初戦の反省も踏まえ、より一人一人が積極的にボールを追いかけることを約束事に追加しました。前半は選手一人一人が約束事を意識し、ひるむことなくボールを追いかけることが出来ました。その成果として予選・決勝を通じて唯一の得点を取ることが出来ました。初戦でも積極的なサッカーをしていたふうかがゴール前での混戦から見事にシュートを決め、リードしたまま前半を終了。後半も引き続き積極的にボールに関与して仲間を助けようと指示を出して送り出しました。
後半、美竹はより積極的にボールを追いかけてくるチームにレベルアップしてきました。
なかなかボールを支配出来ない展開の中、逆転されてしまうと、それまで積極的にボールを追いかけられていた選手の足が少しずつ止まってしまい残念な敗退になりました。
【3試合目】
vs渋谷東部B 結果:0vs5(●)
相手の渋谷東部Bチームは、予選リーグでも負けたチームということでリベンジマッチになります。選手達もリベンジを果たしてやるのだという意気込みと最後まで諦めないガッツを持って試合に臨みます。
ただ、この試合においては、富ヶ谷Bチームの選手の多くがエネルギー切れで動けなくなり、それを頑張って動ける選手がカバーしようとしてフォーメーションが崩壊するという悪循環により、相手に良いようにボールを支配されてしまいリベンジはまた次回に持ち越しになりました。
【課題・改善点】
まだまだ成長の伸びしろがたくさんあるメンバーの試合なので、課題を挙げてしまえばキリがないです。ただ、一番大事なことは、選手達が3試合を通じて「自分の課題が何かを認識しているかどうか」です。急造チームでしたので、フォーメーションやパスワーク等のチームとしての課題は棚に上げてしまって良いかと思います。一方で個人の課題を各選手が挙げられるか、そしてそれを改善するように行動に移せているかどうかが、今後の成長の伸びしろの幅を決めていくものと考えます。試合直後は負けて悔しいと思っていた選手が、試合後1週間以上が経過した今、大小問わず何らかの行動に移せた選手が何人いるでしょうか。
全体的に控えめな性格の選手が多いチームですが、もう1歩早く、大きく踏み出して行動する積極性を持つことが、今の課題を克服し、更なる成長に繋がっていくと信じ、引き続きサッカーに真摯に取り組んでもらいたいと思います。
【良かった点】
最後まで気持ちで諦めてしまった選手がいなかったことです。体力切れで体が動かなってしまっても、最後までなんとかしようともがけたことは、将来的な成長に繋げるための大切な要素なので、今後の成長に期待出来ると考えます。
スポーツにおいて一番成長出来るのは、自分の感覚に自分の身体/運動能力が合わせられるようになる時です。タイミングとしては基礎運動能力が発達する小学校低〜中学年と、肉体的に成長期を迎える中学〜高校の2回のタイミングがあります。
今は基礎運動能力に差があるにせよ、これから迎える成長期でそれをカバーして余りあるくらいに成長出来るタイミングが訪れます。その時に自分が好きなスポーツに一生懸命に取り組めていることが重要で、そのためには「諦めずに頑張れること」はとても大切です。バカにしてくる奴もいるかもしれません(富ヶ谷SCでそんな事をする選手は断じて許しませんが)。でも、今後迎える成長期に、そのような奴らを追い抜くタイミングが必ず来ますので、諦めずに頑張ることがとても大事な成長の鍵になります。
あえて上記では「自分が好きなスポーツ」と書きました。出来ればサッカーを続けていてほしいと思う一方で、人生にはたくさんの選択肢があり、それぞれに無限の可能性がありますので、積極的に自分のやりたいことを見つけ、どんどん一歩を踏み出せる選手・人に成長してもらいたいと願っています。