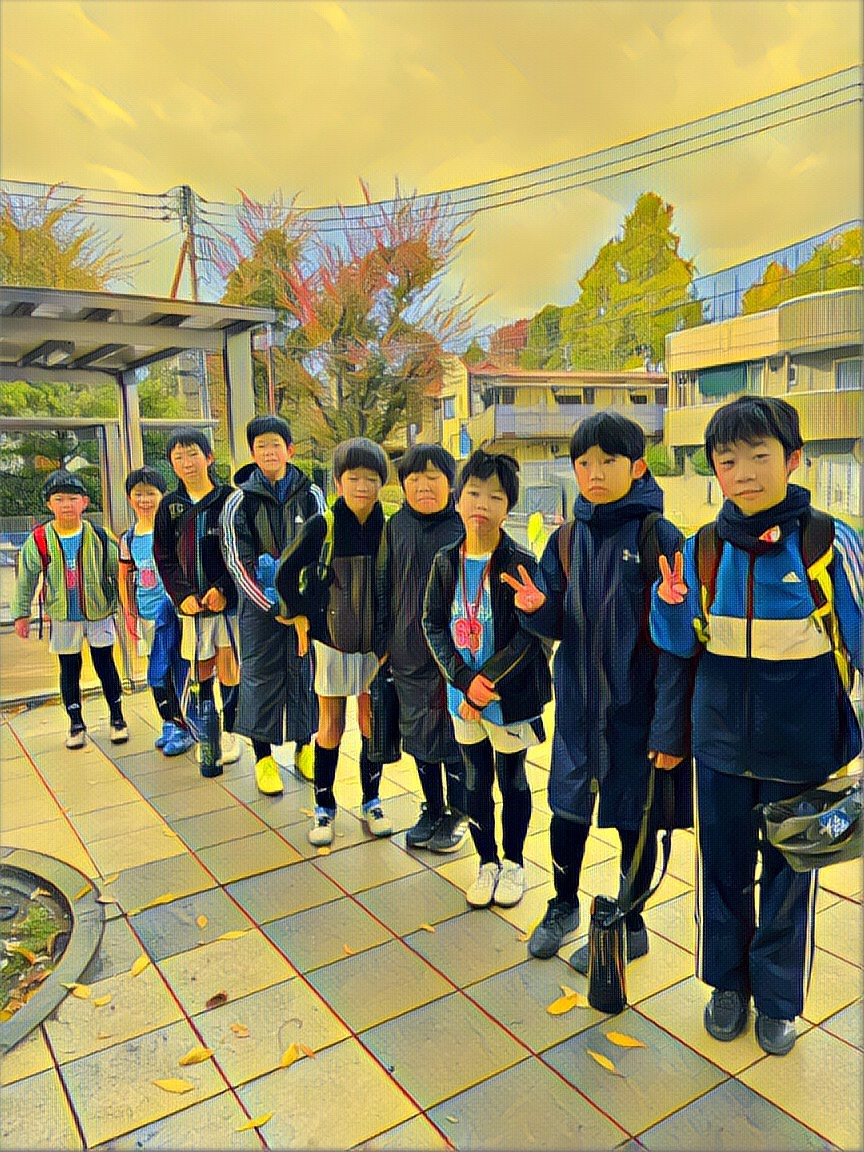コーチの堀口です。
1/11(日) 3連休の中日に開催された4年生秋季大会予選リーグの総括です。
※前回大会が秋季大会だと思っていましたが、実は今回の大会が秋季大会でした。
今回の大会も前回と同じく2-4-1をベースとしたフォーメーションです。
ただ、「ゆうま」の加入があったり3年生の補強でバリエーションを増やす試みをしたりということで1-2-3-1だったり2-3-2だったりとアレンジがありました。
こういったところもこれからも楽しんで見て頂ければと思います。
さて、試合結果ですが、残念ながら0勝2敗1分という結果となりました。
0勝という結果ではありましたが、引き分けの1戦は勝ってもおかしくない試合が出来ていたと思いますし、負けはしましたが最後の1戦も惜しいシーンが何度もあり、勝てるチャンスは十分あったと思います。
一方で、3試合通して開始5分以内の失点が多かったです。
試合開始直後や終了間際の時間帯は得点の動きやすい時間帯です。
この時間帯の集中力を上げていくことも今後の課題の1つとなりそうです。
いくつかの課題が見えたので、それをクリアして次こそは1勝できるようにしていきたいと思います。
■vs セントラルA
●0-13
フォーメーション
前半:2-4-1
後半:1-2-3-1 → 2-4-1
相手はキック力もあり、ドリブルもうまい選手が多いチームでしたが、それ以上に富ヶ谷が消極的になってしまっていたかなと思います。
オフェンスラインとディフェンスラインの間の距離が長くなり、そこを相手に自由に使われた場面が多かったです。
途中はうまく守れていた時間帯もあったので、こういった良かった点は普段からできるようにし、逆に味方との距離感を意識したラインコントロールや1対1は今後の練習で強化していきたいと思います。
開始5分以内の失点は、前後半共に3点ずつあり、後半は終了間際(1分前)にも1失点ありました。
実は、真ん中の5分間の失点は前後半共に1点しかありませんでした。
こう見ると、いかに開始直後に多く失点してしまったかが分かるかと思います。
■vs 猿楽
△2-2 前半 3分:しゅう(えいた:コーナー)、後半 3分:えいた(PK)
フォーメーション
前後半:2-4-1
2位を目指すためにも落とせない1戦であり、選手たちも気合が入っていました。
それは前半に先制点を取るという結果にも表れていたのではないかと思います。
その後点を取られはしましたが、事前にスカウティングした情報を試合前に選手に伝えみんなの意識を合わせたことで、試合中もこまめに調整が出来ていたと思いました。
(後から知りましたが、要注意としていた相手の2番の選手は2年生だったようです。相手にも下の学年に素晴らしい選手がいるのだなと感じました。)
勝てそうな雰囲気もあっただけに残念ではありましたが、見ごたえのある試合になったのではないでしょうか。
ちなみに、開始5分以内の失点は後半の1点のみでした。(前半は6分でした。)
逆に、この試合の富ヶ谷の得点は前後半共に開始3分で、うまくこの時間帯を使って得点できていました。
■vs セントラルC
●1-4 後半 14分:しゅう(ゆう)
フォーメーション
前半:2-3-2 → 2-4-1
後半:2-4-1
この日最後の試合ということもあり、これまでキーパーで頑張ってくれた「かい」にフィールドでのプレーをさせてあげるため「えいた」がキーパーを引き受けてくれました。「えいた」ありがとう!
試合としては、大量得点で勝たないと2位になれないというプレッシャーもあったかもしれませんが、猿楽と互角の勝負ができたことから少し油断があったかもしれません。
この日全体を通しての課題ですが、この試合でも前後半共に開始5分以内に1失点しています。
見た目ではそれほど分かりませんでしたが、もしかしたらこれで「点を取らないと」と焦る気持ちが生まれてしまい、結果として失点が増えてしまったのかもしれません。
それでもこの試合良かったのは、最後まで点を取ることをあきらめなかったことだと思います。
後半終了間際の14分に1点返すことができ、さらにもう1点取るぞという勢いで、自分たちですぐさまボールをセンターサークルに戻してセットするというプレーが見られました。
最後の最後までもう1点取れそうな雰囲気があり自然と熱の入る瞬間だったのではないかと思います。
こういった勢いや雰囲気ををいつでも作れるようになるともっと自分たちのペースで試合ができるようになるのでモチベーションのコントロールという面でも強化していけると良いと思っています。
--- 個人へのコメント ---
☆ひろと
今回ゲームキャプテンをお願いしました。
大会前後のあいさつやゲーム前のコイントスなどしっかりチームを引っ張ってくれたと思います。
試合に関しては、今回もフィールドを駆け回ってくれました。
また、ボランチの位置からゲームの組み立ての為のドリブルやパスにチャレンジしてくれていたと思います。
今後の伸びしろ:
ゲームメイクについて、アイデアは良いものを持っているように見えましたが、技術が追いついていないかなという印象なので、足元の技術(ボールタッチ)とパスの技術を磨くことでそのアイデアを活かせるようになると思います。
また、DFについては、相手とぶつかりあえる状況(フィジカルコンタクトで勝負できる状況)では強さを発揮できますが、今回のセントラルAのように触らせてもらえないドリブルをされるとその強みも活かしきれなくなります。
相手の動きを読んで、行く先の妨害もうまくできるようにしていきましょう。
☆さえ
右サイドで諦めずにボールを追い、前線へのつなぎに貢献してくれました。
特に3試合目は献身的に走り、ボールをつないでくれていました。
また、ポジションの意識もかなりついてきたようで、状況によって逆サイドにフォローに来た後、周りを確認して自分のサイドにすぐに戻っていくようなプレーも見られました。
今後の伸びしろ:
本人は「自分はあまり動かない」と言っていましたが、3試合目のようにしっかり動き回れることを知っています。
ただ、エンジンがかかるのが遅い時があるので、最初からエンジンをかけられようにモチベーションをコントロールできるようになると良いと思います。
あと、急いで守備に戻るのはとても良いのですが、ボールを見ながら戻りましょう。
☆みどり
ボールが出る相手の所にうまく寄せていたと思います。
特に、モチベーションを高く保てている時は感や頭を働かせた先読みプレーが出来ているように思えます。
最近はMFのサイドのポジションをやることが多いですが、献身的にディフェンスもこなしてくれます。
今後の伸びしろ:
体をぶつけて強引に奪い取るプレーは苦手に見えるので、逆に頭を使ってスマートに奪う方法を身に着けると良いかもしれません。
そのためには、ボールの位置だけでなく、相手の重心の位置や目の動きなどから次の動きを予測することをやってみると良いと思います。
また、試合中髪の毛が邪魔になるのか、右手で押さえながらプレーするシーンも見られました。
走力があり、最近はキックもうまくなってきているので、これでバランスが悪くて思うようなプレーができないともったいないかなと思いました。
☆ゆう
色々な場所に顔を出してボールに絡んでくれました。
また、少し強引にでもボールを持ち出して攻撃につなげるシーンも見られました。
今後の伸びしろ:
今回のように、球際の寄せが早くスピードを活かしたプレーが出来ないような相手の場合でも
密集地帯でもかわせるドリブルテクニックを身に着けられるともっとチャンスを作れると思います。
また、トップ下の位置でのプレーも多かったので相手の裏に飛び出すタイミングが難しかったのかもしれませんが、トップやサイドの選手とうまく連携して自分が飛び出せる状況を作り出せると、自分がトップをやるときも裏抜け以外の選択肢を持てるようになり、攻撃に幅が出てくると思います。
☆ゆうま
まだ技術が追いついていない分はフィールドを駆け回ることで十分にカバーしてくれたと思います。
サッカーのブランクがある中、再開してまだ2ヶ月くらいだと思いますが、この期間しっかり練習した成果がキックオフでのキックや相手へのプレスからボール奪取という場面で随所に見られたと思います。
今後の伸びしろ:
オフサイドやスローインといった2年生までは細かくやってこなかったルールへの対応や戦術の理解というところを今後やっていきましょう。
また、足元の技術は練習量に比例してうまくなるので、地道ですがコツコツ練習を積み重ねていきましょう。
吸収力もやる気も十分あると思うので、すぐにみんなに追いつけると思います。
☆えいた
ゴールに向かって果敢にチャレンジしてくれました。
その結果が猿楽戦でのPK獲得だと思います。
また、率先してGKもやってくれました。ありがとう!
今後の伸びしろ:
ドリブル突破でチャンスを掴むことも多いですが、周りに預けると楽に運べるケースや得点の可能性が上がるケースがありました。
オフ・ザ・ボールやドリブル中に周りを見てパスの選択肢も持っておけるともっと良いと思います。
☆がく
前も後ろもできるプレーヤーです。
今の4年生チームの補強メンバーとしてはディフェンスもしっかりできるメンバーが欲しいので、そういった意味でもとても頼りになります。
今後の伸びしろ:
相手DFがしっかりついている状態でディフェンスラインの位置からドリブルを始めると、相手ゴール前まで運ぶ前に力尽きてしまいます。
ドリブルで仕掛けるタイミング、パスを出した後やパスをもらうための動きを工夫することでもっとラストパスやシュートまで行ける回数が増えると思います。
☆たついち
ゴール前の最後の最後でブロックしてくれる場面が多く、かなりの失点を防いでくれたと思います。
また、ボールを奪った後などに一旦落ち着いて出しどころを探したり一人かわしてからパスするなどDFとしての安定感が増したと思います。
今後の伸びしろ:
味方のMFやDFと連携してボールを奪うプレーが身につくと今以上に安定して守れるようになります。
そのためにもディフェンス時でも周りの状況を見てポジショニングや時には指示の声出しもできるようになると良いと思います。
☆かい
飛び出しのタイミングが素晴らしくスペースのボールをかなりクリアしてくれていました。
また1対1の場面でも素晴らしいタイミングで飛び出し、見事防いでくれました。
試合中に相手チームのコーチの声が聞こえてきましたが、「あのキーパーうまいぞ」と言っていました。
今後の伸びしろ:
素晴らしいタイミングで飛び出した後、キャッチできる場面でも蹴ってしまうことが多いように見えました。
キャッチできるところはキャッチできるようになるともっとチーム全体を落ち着かせることが出来るようになります。
☆しゅう
サッカーをよく知っているプレーを随所に見せてくれました。
特にセントラルC戦で見せたフリーキックからの素早いリスタートが素晴らしかったです。
相手コーナーキックで、相手がほとんど全員上がってきている状態だったため、直後に得たフリーキックの場面では相手陣内にDFが1人もいない状況になっていました。
この時、素早いリスタートから右前に張っていた「かい」へのパスで一気にチャンスを作ってくれました。
コーナーキックを蹴る時点から奪った後の狙いがそこであることを理解していたのだと思います。
今後の伸びしろ:
攻撃面では申し分ないですが、ボランチという意味では少し上がりすぎて守りが手薄になる場面が見られました。
ポジションごとのオフェンスとディフェンスのバランスを踏まえてプレーできるともっと良いと思います。
また、慣れないDFという事もあったと思いますが、ボールキープがしっかり出来ると思うので、どの位置でも冷静にプレーできると良いです。
☆そうじ
ディフェンスでも奮闘してくれましたが、特に目を引いたプレーは3戦目のパスでした。
3戦目の後半の戦術として、相手のキーパーとディフェンスラインの間に落とすボールを出してトップの選手はそこめがけて突破しようというのがありましたが、その注文に応える素晴らしいキックを見せてくれました。
今後の伸びしろ:
ディフェンス時のポジショニングや相手との距離感で、自分の一番得意な距離を把握するとディフェンス力が上がります。
また、キックが持ち味の1つだと思うので、混戦時でも落ち着いて狙って前線につなげられるように意識すると良いと思います。
1/11(日) 3連休の中日に開催された4年生秋季大会予選リーグの総括です。
※前回大会が秋季大会だと思っていましたが、実は今回の大会が秋季大会でした。
今回の大会も前回と同じく2-4-1をベースとしたフォーメーションです。
ただ、「ゆうま」の加入があったり3年生の補強でバリエーションを増やす試みをしたりということで1-2-3-1だったり2-3-2だったりとアレンジがありました。
こういったところもこれからも楽しんで見て頂ければと思います。
さて、試合結果ですが、残念ながら0勝2敗1分という結果となりました。
0勝という結果ではありましたが、引き分けの1戦は勝ってもおかしくない試合が出来ていたと思いますし、負けはしましたが最後の1戦も惜しいシーンが何度もあり、勝てるチャンスは十分あったと思います。
一方で、3試合通して開始5分以内の失点が多かったです。
試合開始直後や終了間際の時間帯は得点の動きやすい時間帯です。
この時間帯の集中力を上げていくことも今後の課題の1つとなりそうです。
いくつかの課題が見えたので、それをクリアして次こそは1勝できるようにしていきたいと思います。
■vs セントラルA
●0-13
フォーメーション
前半:2-4-1
後半:1-2-3-1 → 2-4-1
相手はキック力もあり、ドリブルもうまい選手が多いチームでしたが、それ以上に富ヶ谷が消極的になってしまっていたかなと思います。
オフェンスラインとディフェンスラインの間の距離が長くなり、そこを相手に自由に使われた場面が多かったです。
途中はうまく守れていた時間帯もあったので、こういった良かった点は普段からできるようにし、逆に味方との距離感を意識したラインコントロールや1対1は今後の練習で強化していきたいと思います。
開始5分以内の失点は、前後半共に3点ずつあり、後半は終了間際(1分前)にも1失点ありました。
実は、真ん中の5分間の失点は前後半共に1点しかありませんでした。
こう見ると、いかに開始直後に多く失点してしまったかが分かるかと思います。
■vs 猿楽
△2-2 前半 3分:しゅう(えいた:コーナー)、後半 3分:えいた(PK)
フォーメーション
前後半:2-4-1
2位を目指すためにも落とせない1戦であり、選手たちも気合が入っていました。
それは前半に先制点を取るという結果にも表れていたのではないかと思います。
その後点を取られはしましたが、事前にスカウティングした情報を試合前に選手に伝えみんなの意識を合わせたことで、試合中もこまめに調整が出来ていたと思いました。
(後から知りましたが、要注意としていた相手の2番の選手は2年生だったようです。相手にも下の学年に素晴らしい選手がいるのだなと感じました。)
勝てそうな雰囲気もあっただけに残念ではありましたが、見ごたえのある試合になったのではないでしょうか。
ちなみに、開始5分以内の失点は後半の1点のみでした。(前半は6分でした。)
逆に、この試合の富ヶ谷の得点は前後半共に開始3分で、うまくこの時間帯を使って得点できていました。
■vs セントラルC
●1-4 後半 14分:しゅう(ゆう)
フォーメーション
前半:2-3-2 → 2-4-1
後半:2-4-1
この日最後の試合ということもあり、これまでキーパーで頑張ってくれた「かい」にフィールドでのプレーをさせてあげるため「えいた」がキーパーを引き受けてくれました。「えいた」ありがとう!
試合としては、大量得点で勝たないと2位になれないというプレッシャーもあったかもしれませんが、猿楽と互角の勝負ができたことから少し油断があったかもしれません。
この日全体を通しての課題ですが、この試合でも前後半共に開始5分以内に1失点しています。
見た目ではそれほど分かりませんでしたが、もしかしたらこれで「点を取らないと」と焦る気持ちが生まれてしまい、結果として失点が増えてしまったのかもしれません。
それでもこの試合良かったのは、最後まで点を取ることをあきらめなかったことだと思います。
後半終了間際の14分に1点返すことができ、さらにもう1点取るぞという勢いで、自分たちですぐさまボールをセンターサークルに戻してセットするというプレーが見られました。
最後の最後までもう1点取れそうな雰囲気があり自然と熱の入る瞬間だったのではないかと思います。
こういった勢いや雰囲気ををいつでも作れるようになるともっと自分たちのペースで試合ができるようになるのでモチベーションのコントロールという面でも強化していけると良いと思っています。
--- 個人へのコメント ---
☆ひろと
今回ゲームキャプテンをお願いしました。
大会前後のあいさつやゲーム前のコイントスなどしっかりチームを引っ張ってくれたと思います。
試合に関しては、今回もフィールドを駆け回ってくれました。
また、ボランチの位置からゲームの組み立ての為のドリブルやパスにチャレンジしてくれていたと思います。
今後の伸びしろ:
ゲームメイクについて、アイデアは良いものを持っているように見えましたが、技術が追いついていないかなという印象なので、足元の技術(ボールタッチ)とパスの技術を磨くことでそのアイデアを活かせるようになると思います。
また、DFについては、相手とぶつかりあえる状況(フィジカルコンタクトで勝負できる状況)では強さを発揮できますが、今回のセントラルAのように触らせてもらえないドリブルをされるとその強みも活かしきれなくなります。
相手の動きを読んで、行く先の妨害もうまくできるようにしていきましょう。
☆さえ
右サイドで諦めずにボールを追い、前線へのつなぎに貢献してくれました。
特に3試合目は献身的に走り、ボールをつないでくれていました。
また、ポジションの意識もかなりついてきたようで、状況によって逆サイドにフォローに来た後、周りを確認して自分のサイドにすぐに戻っていくようなプレーも見られました。
今後の伸びしろ:
本人は「自分はあまり動かない」と言っていましたが、3試合目のようにしっかり動き回れることを知っています。
ただ、エンジンがかかるのが遅い時があるので、最初からエンジンをかけられようにモチベーションをコントロールできるようになると良いと思います。
あと、急いで守備に戻るのはとても良いのですが、ボールを見ながら戻りましょう。
☆みどり
ボールが出る相手の所にうまく寄せていたと思います。
特に、モチベーションを高く保てている時は感や頭を働かせた先読みプレーが出来ているように思えます。
最近はMFのサイドのポジションをやることが多いですが、献身的にディフェンスもこなしてくれます。
今後の伸びしろ:
体をぶつけて強引に奪い取るプレーは苦手に見えるので、逆に頭を使ってスマートに奪う方法を身に着けると良いかもしれません。
そのためには、ボールの位置だけでなく、相手の重心の位置や目の動きなどから次の動きを予測することをやってみると良いと思います。
また、試合中髪の毛が邪魔になるのか、右手で押さえながらプレーするシーンも見られました。
走力があり、最近はキックもうまくなってきているので、これでバランスが悪くて思うようなプレーができないともったいないかなと思いました。
☆ゆう
色々な場所に顔を出してボールに絡んでくれました。
また、少し強引にでもボールを持ち出して攻撃につなげるシーンも見られました。
今後の伸びしろ:
今回のように、球際の寄せが早くスピードを活かしたプレーが出来ないような相手の場合でも
密集地帯でもかわせるドリブルテクニックを身に着けられるともっとチャンスを作れると思います。
また、トップ下の位置でのプレーも多かったので相手の裏に飛び出すタイミングが難しかったのかもしれませんが、トップやサイドの選手とうまく連携して自分が飛び出せる状況を作り出せると、自分がトップをやるときも裏抜け以外の選択肢を持てるようになり、攻撃に幅が出てくると思います。
☆ゆうま
まだ技術が追いついていない分はフィールドを駆け回ることで十分にカバーしてくれたと思います。
サッカーのブランクがある中、再開してまだ2ヶ月くらいだと思いますが、この期間しっかり練習した成果がキックオフでのキックや相手へのプレスからボール奪取という場面で随所に見られたと思います。
今後の伸びしろ:
オフサイドやスローインといった2年生までは細かくやってこなかったルールへの対応や戦術の理解というところを今後やっていきましょう。
また、足元の技術は練習量に比例してうまくなるので、地道ですがコツコツ練習を積み重ねていきましょう。
吸収力もやる気も十分あると思うので、すぐにみんなに追いつけると思います。
☆えいた
ゴールに向かって果敢にチャレンジしてくれました。
その結果が猿楽戦でのPK獲得だと思います。
また、率先してGKもやってくれました。ありがとう!
今後の伸びしろ:
ドリブル突破でチャンスを掴むことも多いですが、周りに預けると楽に運べるケースや得点の可能性が上がるケースがありました。
オフ・ザ・ボールやドリブル中に周りを見てパスの選択肢も持っておけるともっと良いと思います。
☆がく
前も後ろもできるプレーヤーです。
今の4年生チームの補強メンバーとしてはディフェンスもしっかりできるメンバーが欲しいので、そういった意味でもとても頼りになります。
今後の伸びしろ:
相手DFがしっかりついている状態でディフェンスラインの位置からドリブルを始めると、相手ゴール前まで運ぶ前に力尽きてしまいます。
ドリブルで仕掛けるタイミング、パスを出した後やパスをもらうための動きを工夫することでもっとラストパスやシュートまで行ける回数が増えると思います。
☆たついち
ゴール前の最後の最後でブロックしてくれる場面が多く、かなりの失点を防いでくれたと思います。
また、ボールを奪った後などに一旦落ち着いて出しどころを探したり一人かわしてからパスするなどDFとしての安定感が増したと思います。
今後の伸びしろ:
味方のMFやDFと連携してボールを奪うプレーが身につくと今以上に安定して守れるようになります。
そのためにもディフェンス時でも周りの状況を見てポジショニングや時には指示の声出しもできるようになると良いと思います。
☆かい
飛び出しのタイミングが素晴らしくスペースのボールをかなりクリアしてくれていました。
また1対1の場面でも素晴らしいタイミングで飛び出し、見事防いでくれました。
試合中に相手チームのコーチの声が聞こえてきましたが、「あのキーパーうまいぞ」と言っていました。
今後の伸びしろ:
素晴らしいタイミングで飛び出した後、キャッチできる場面でも蹴ってしまうことが多いように見えました。
キャッチできるところはキャッチできるようになるともっとチーム全体を落ち着かせることが出来るようになります。
☆しゅう
サッカーをよく知っているプレーを随所に見せてくれました。
特にセントラルC戦で見せたフリーキックからの素早いリスタートが素晴らしかったです。
相手コーナーキックで、相手がほとんど全員上がってきている状態だったため、直後に得たフリーキックの場面では相手陣内にDFが1人もいない状況になっていました。
この時、素早いリスタートから右前に張っていた「かい」へのパスで一気にチャンスを作ってくれました。
コーナーキックを蹴る時点から奪った後の狙いがそこであることを理解していたのだと思います。
今後の伸びしろ:
攻撃面では申し分ないですが、ボランチという意味では少し上がりすぎて守りが手薄になる場面が見られました。
ポジションごとのオフェンスとディフェンスのバランスを踏まえてプレーできるともっと良いと思います。
また、慣れないDFという事もあったと思いますが、ボールキープがしっかり出来ると思うので、どの位置でも冷静にプレーできると良いです。
☆そうじ
ディフェンスでも奮闘してくれましたが、特に目を引いたプレーは3戦目のパスでした。
3戦目の後半の戦術として、相手のキーパーとディフェンスラインの間に落とすボールを出してトップの選手はそこめがけて突破しようというのがありましたが、その注文に応える素晴らしいキックを見せてくれました。
今後の伸びしろ:
ディフェンス時のポジショニングや相手との距離感で、自分の一番得意な距離を把握するとディフェンス力が上がります。
また、キックが持ち味の1つだと思うので、混戦時でも落ち着いて狙って前線につなげられるように意識すると良いと思います。